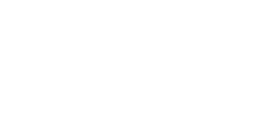近江麻布
豊かな自然と
伝統が作り出す
美しい物語

原始の時代に気温の変化や外傷から身を守るために人類は衣を身に纏うことを始めました。動物の皮から始まり、容易く手に入る自然の植物へと素材は変化していきます。植物の繊維を経糸と緯糸にして道具を使って布を織るというのは、画期的な発明でした。道具を使うことにより生産性は上がり、布は自給自足から人々の生活を営むための仕事、産業となっていきます。
近江は、室町の時代から良質な麻織物の産地として知られていました。
近江の持つ環境が麻布を発展させ、また、現代まで続く長い歴史がその価値を高めています。

発展の背景
滋賀県は周囲を鈴鹿、伊吹、比良、比叡の山々に囲まれ、中央に県の面積の6分の1を占める日本で一番大きな湖「琵琶湖」があります。琵琶湖には400を超える大小さまざまな河川が注いでおり、その河川の中には下流部で状流し清らか水を生み出す湧水地を育むものがあります。繊維産業は大量の清水を使うことから、これらの水を利用して、滋賀県では湖東地域の麻織物、湖西地域の綿織物、湖北地域の絹織物、とそれぞれの地域で繊維産業が発展してきました。
湖東地域の愛知川や宇曽川の扇状地では中山道の交差する付近に湧水地が見られ、滋賀県の麻織物は、これらの自然がもたらす恵みによって育まれてきました。また、乾燥すると切れやすい麻織物にとっては、琵琶湖のもたらす湿潤な気候も最適でした。
もう一つ産業の発展に大きな要因となったのが街道です。近江の湖東地域は、古きより東西の地域を結ぶ交通の要所にあたり多くの街道が整備されてきました。これらの街道を通じて麻布は流通し繊維産業の一段の発展につながりました。
歴史
滋賀県の麻織物の歴史は室町時代に遡ります。その最古の記録は、宝徳元年(1449)に近江国高島郡と越前国敦賀の神官が京都吉田家への土産として「高宮五端」を持参したことが書かれている吉田家の社家の鈴木氏の日記です。永正13年(1516)には京極高清が「細美五端」を足利幕府へ、文禄元年(1592)には多賀大社の神職が朝鮮出兵への陣中見舞いとして豊臣秀吉に「帷子五端」を送ったことがそれぞれ記録されており、室町時代にはすでに産業としての麻布の生産は始まっており、また、一種の高級品として珍重されていたことがわかります。その後、江戸時代になると越後縮や奈良晒と並ぶ良質な麻織物「高宮布」の産地としてその地位を築きました。様々な書物のその名声が書かれるようになります。
明治に入り生産拠点が愛知郡(現在の東近江市)へと移り、近代化に伴う技術核心、生産組織の確立などを経て麻織物の産地として発展し続けてきました。


高宮布
「高宮布」とは室町時代から江戸時代にかけて湖東地域で生産された麻布のことで、中山道高宮宿が麻布の集積地であったことから「高宮布」の名が生まれました。高宮宿は宿場町であったことに加え、多賀大社の門前町であり、中山道を行き交う人や多賀大社への参拝客で多くの人で大変賑わいました。文化11年(1814)「近江名所図会」には「高宮嶋」「織元」と書かれた布をかけた店先があり、天保14年(1843)「枝村より高宮宿縮図」には、高宮宿の町並で十数軒の布商売が記されいます。参拝や街道の土産物として、近江商人の商品として、その名声は全国に広がっていきました。彦根藩は「高宮布」を保護統制し、幕府への毎年の献上品に加え各方面への贈答品としました。